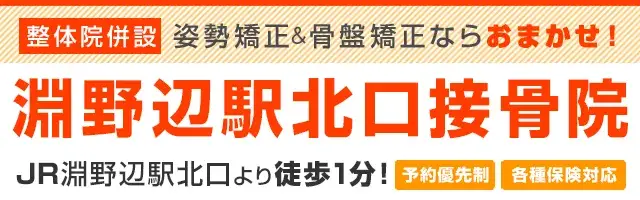オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

膝の下あたりに痛みが出る
膝の下あたりに腫れている
ジャンプや走るなどの運動を行う時に、膝に痛みが出る
膝の下あたりを押すと痛みがある
運動後に膝に痛みが出る
オスグッドについて知っておくべきこと

成長期の子どもや若者に多く見られます。
特にスポーツ活動が活発なお子さまに発生しやすく、膝の前面にある脛骨に対する過度なストレスが原因で、成長板に炎症が生じてしまったり、骨に引っ張られるストレスが加わることで、骨が剥離してしまう場合があり、強い痛みが出ることがあります。
そのまま痛みを我慢して無理に運動を続けてしまうと、状態が悪化してしまい、施術だけでは対応が難しくなるケースもあります。
予防には、大腿四頭筋という太ももの前側の筋肉の柔軟性を高めることが効果的とされており、入浴時のマッサージやストレッチ、さらに症状が軽減した後も予防のためにストレッチを継続することが望ましいです。
症状の現れ方は?

オスグッドは、小学生から中学生の成長期にあたる男児に多いとされています。運動時や運動後に痛みが現れ、膝のお皿の下にある脛骨と呼ばれる骨が突出したり、赤く腫れたりすることがあります。
初期の段階では、圧迫や正座をすることで脛骨の骨膜が引っ張られて痛みが出るものの、運動ができないほどではないため、無理をして悪化させてしまうケースが非常に多く見られます。
明らかなケガの記憶がないため、「痛いけれど動ける」「ただの成長痛だろう」と判断し、無理に運動を続けてしまうと、長期間の運動休止が必要になったり、外科的な施術が必要となる場合もあるため、早めの対応がとても大切な疾患です。
その他の原因は?

オスグッド病の原因として、未成熟な骨が多数存在する成長期に多く見られ、小学校高学年から中学生の頃に多く発症します。
この時期は、クラブ活動や部活動などにこれまで以上に熱心に取り組むことが多くなる年代でもあります。
ちょうど男児の成長期と重なるため、身長が急激に伸びるお子さまも少なくありませんが、筋肉や腱などの軟部組織は骨と同じように成長できないため、成長期には太ももの前側にある筋肉の柔軟性が低下し、硬くなってしまうことがよくあります。
このように硬くなった筋肉が膝の下にある脛骨という骨を継続的に引っ張ることで、剥離骨折が起こり、骨の変形につながる場合があります。
オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッド病は、目立った外傷がなく、患者さまが子どもであることが多いため、運動を休止することが難しいケースもあると考えられます。
しかし、痛みを我慢して運動を続けていると、筋肉に過度な負担がかかり、変形が生じたり、痛みが強くなってしまうことも少なくありません。
その結果、無理をしたことにより、かえって長期間の運動休止が必要になったり、外科的な施術や手術が検討される場合もあります。さらに、大人になってから、当時の無理が影響し、「オスグッド後遺症」と呼ばれる症状が現れることもあります。
「動けるから」と我慢せず、早めのケアと医療機関の受診をお勧めいたします。
当院の施術方法について

当院の施術方法としては、硬くなってしまった大腿四頭筋をゆるめるための鍼灸施術や、筋肉をゆるめた後の柔軟性を高めるための筋膜ストレッチ、さらに骨盤の歪みを整えて筋肉への負担を軽減する骨盤矯正などの施術があります。
硬くなった大腿四頭筋をゆるめ、筋膜ストレッチにより身体全体を覆っている「筋膜」と呼ばれるボディスーツのような膜の柔軟性とバランスを調整することで、筋肉が付着している骨膜と呼ばれる骨の周囲の膜にかかるストレスの軽減が期待できます。
また、骨盤や骨格に歪みがあると、足の向きが外側に開いてしまい、骨が本来の位置から逸脱してしまうことがあります。その結果、筋肉に過剰な引っ張りが生じるため、骨盤や骨格を整えることで、痛みの根本的な要因である歪みの軽減が期待できます。
改善していく上でのポイント

軽減を目指すうえでのポイントは、長期間我慢せずに早期に施術やケアを始めること、無理に使い続けないこと、大腿四頭筋の硬さをいかにゆるめるか、柔軟性をどのように確保するか、そして骨格の歪みなどを整えて筋肉や身体の使い方をスムーズにすることです。
まずは患部を休め、痛みが強い場合には安静にし、アイシング(冷却)を行い、十分な休息や栄養を取ることで、痛みの軽減を目指します。
運動に復帰する際には、運動前後に大腿四頭筋のストレッチを入念に行い、軽めの運動から始めることや、痛みが出ない範囲の運動にメニューを見直すことも大切なポイントです。