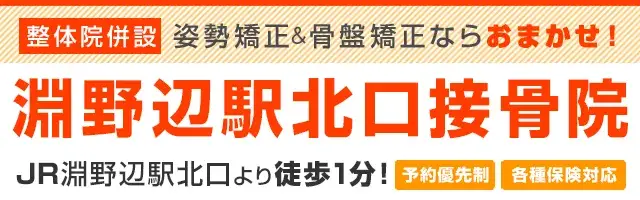オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

膝の下あたりに痛みが出る
膝の下あたりに腫れがある
ジャンプや走るなどの運動を行う際、膝に痛みが出る
膝の下あたりを押すと痛みがある
運動後に膝に痛みが出る
オスグッドについて知っておくべきこと

成長期の子どもや若者に多く見られる症状です。
特にスポーツ活動が活発なお子さまに発症しやすく、膝の前面にある脛骨に対する過度なストレスが原因で、成長板に炎症が生じたり、骨に引っ張られる力が加わることで骨が剥離してしまったりすることがあります。その結果、強い痛みを感じるようになります。
また、痛みを我慢して運動を無理に続けてしまうと、症状が悪化し、最終的に手術が必要となる可能性もあります。
予防としては、大腿四頭筋という太ももの前側の筋肉の柔軟性を高めることが大切です。入浴時のマッサージやストレッチを行い、症状が軽減した後も予防のためにストレッチを継続することが望ましいです。
症状の現れ方は?

オスグッドは、小学生から中学生の成長期にあたる男児に多く見られる症状です。運動時や運動後に膝の痛みが現れ、脛骨と呼ばれる膝のお皿の下の骨が突出したり、赤く腫れたりすることがあります。
初期には、圧迫や正座をすることで脛骨の骨膜が引っ張られ、痛みが出ることがありますが、運動がまったくできないほどではないため、無理をしてしまい悪化させてしまうケースが多く見受けられます。
明らかなケガではない、痛みはあっても動ける、ただの成長痛だと思い込んで放置し、無理に運動を続けてしまうことで、長期間の運動休止や外科的な施術が必要になる場合もあります。そのため、早期の対応が非常に大切な症状です。
その他の原因は?

オスグッド病の原因として、未成熟な骨が多く存在する成長期に発症しやすく、小学校高学年から中学生の時期に多く見られます。
この年代になると、クラブ活動や部活動などにこれまで以上に熱心に取り組むお子さまが多くなります。
また、この時期はちょうど男児の成長期と重なり、急激に身長が伸びるお子さまも少なくありません。ただし、筋肉や腱などの軟部組織は骨と同じスピードで成長するわけではないため、成長期には太ももの前側の筋肉の柔軟性が低下し、硬くなってしまうことが多くなります。
その結果、硬くなった筋肉が膝の下にある脛骨という骨を繰り返し引っ張ることで、骨に過度な負担がかかり、剥離骨折が起こって変形につながることもあります。
オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッド病は、目立った外傷がなく、患者さまが子どもであることが多いため、運動を休止することが難しいケースもあるかと思います。
しかしながら、痛みを我慢して運動を続けてしまうと、筋肉に過度な負荷がかかり、骨の変形が進んでしまったり、痛みが強くなってしまうことも少なくありません。
その結果、無理をしたことでかえって長期の運動休止が必要になったり、外科的な処置や手術が必要となる場合もあります。また、無理をした影響が大人になってから現れ、「オスグッド病後遺症」と呼ばれる症状が出てしまうこともあります。
「まだ動けるから」と我慢せず、できるだけ早めに適切なケアや医療機関の受診を心がけることをおすすめいたします。
当院の施術方法について

当院の施術方法としては、硬くなってしまった大腿四頭筋をゆるめるための鍼灸施術や、筋肉をゆるめた後に柔軟性を高める筋膜ストレッチ、筋肉への負荷を軽減する骨盤矯正などの施術をご用意しております。
硬くなった大腿四頭筋をゆるめたうえで、筋膜ストレッチにより身体全体を覆っている筋膜(ボディスーツのような膜)の柔軟性とバランスを整えることで、筋肉が付着している骨膜(骨の周囲にある膜)へのストレスを軽減することが期待できます。
さらに、骨盤や骨格の歪みがあると、足の向きが外側に開きやすくなり、骨の本来あるべき位置からずれてしまうことで筋肉が余計に引っ張られてしまいます。そのため、骨盤や骨格を整えることで、痛みの根本的な要因と考えられる歪みにアプローチすることもおすすめです。
改善していく上でのポイント

軽減が期待できるためのポイントは、長期間我慢せずに早期の施術やケアを始めること、無理をして使い続けないこと、大腿四頭筋の硬さをいかにゆるめるか、そして柔軟性をしっかりと確保することです。また、骨格の歪みを減らし、筋肉や身体の使い方を適切にすることも重要なポイントになります。
まずは患部をしっかりと休め、痛みが強い場合は安静にし、アイシング(冷却)を行いながら、十分な休息と栄養を取り入れて痛みを軽減させることが大切です。
復帰にあたっては、運動前後に大腿四頭筋のストレッチを丁寧に行うことが望ましく、軽めの運動から段階的に取り入れることや、痛みが出ない範囲での練習メニューに見直すことも大切なポイントです。
監修

淵野辺駅北口接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:神奈川県大和市
趣味・特技:筋トレ、家族サービス、子育て